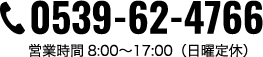余談~牛糞堆肥は濃くなっている!?
風が吹けば桶屋が儲かる…ではないですが、木質バイオマス発電ができれば木造住宅が減れば牛糞堆肥の肥料成分は濃くなる。というのはあながち変な理屈ではありません。
牛糞堆肥は牛糞に副資材を混合して作ることが多いですが、これまでリサイクル工場から出る木質チップや材木工場から出るおがくずなどを副資材に利用してきました。ところが木質バイオマス発電所が各地にできるのに伴い、従来は畜産農家に回っていた木質チップがバイオマス発電所にとられることに。また国内の木材需要が減少することでおがくずの発生量も減少…。畜産農家さんから思うように副資材が手に入らないという声は非常に多く聞くようになりました。
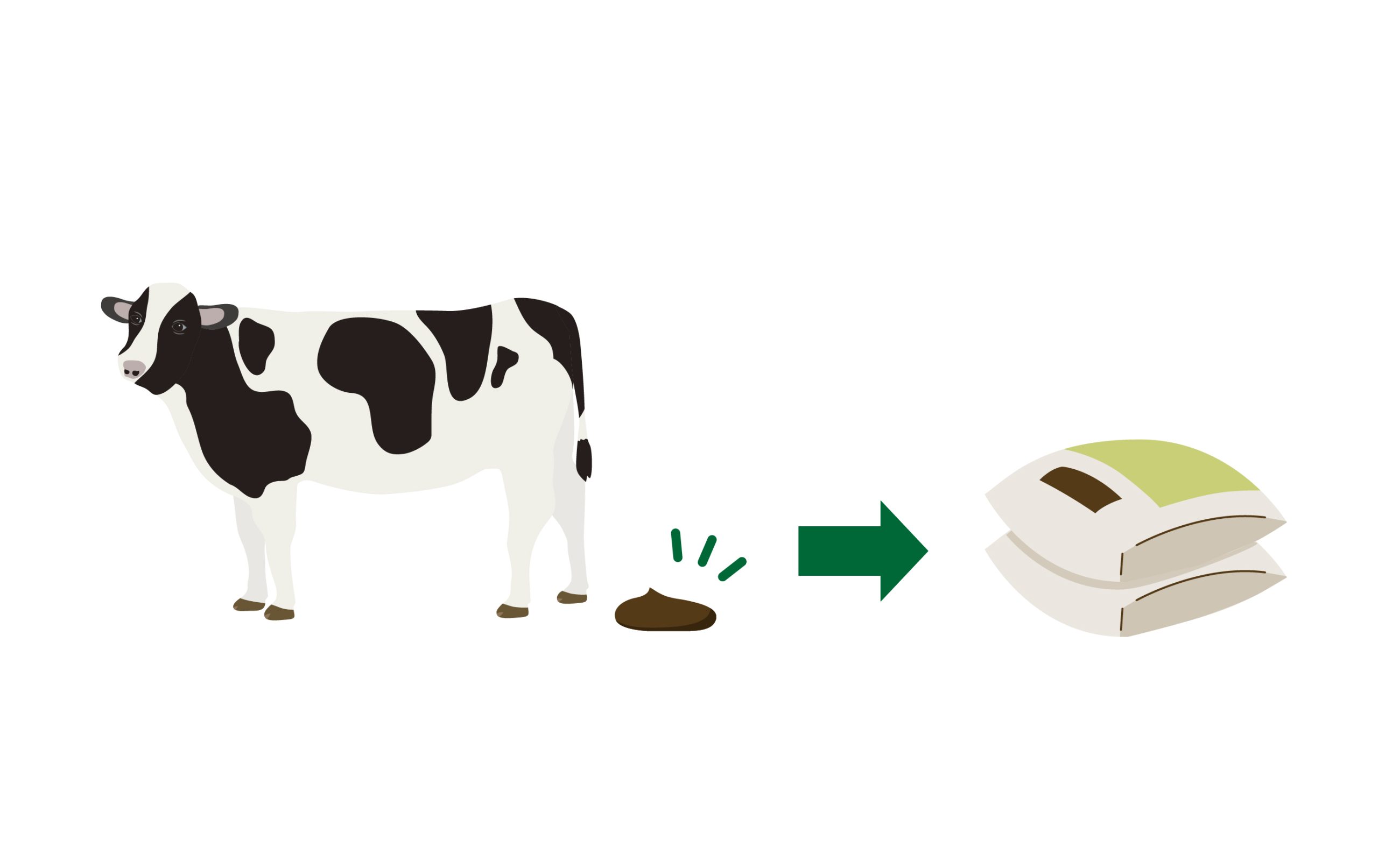
しかし生のふん尿は何かしら添加しなければ水分が多すぎてうまく堆肥化しません。そこで、「戻し堆肥」といって、すでに堆肥になった牛糞、あるいは堆肥になりつつある中熟牛糞堆肥を生のふん尿に混ぜて利用し、再度堆肥化させていく方法をとることも多く行われるようになりました。しかも今は家畜ふん尿由来の堆肥は屋根の下で作らなくてはならないため雨による肥料成分の流亡がそもそも少なく、ただでさえ肥料濃度は昔に比べれば上がっています。そこに「戻し堆肥」を行えば当然肥料成分はさらに濃くなります。
静岡県で1978年と2018年を比較したところ、40年で窒素が3倍、リン酸も3倍、カリが2倍になったというデータもあります。
プラスに考えればそれだけ元肥も削減できると考えることもできます。一方で想像以上に肥料成分があるかも…ということを念頭において、
特に施設栽培などでは施肥することも大切です。
◆堆肥の肥料成分は効くんか?
堆肥の中に含まれる主要肥料成分・NPKのうち、カリは90%以上肥料として期待できると言われています。リン酸は文献やデータによって若干違いはありますが、おおむね動物性堆肥で60~90%、特に鶏、豚、肉牛は肥効率が80~90%と高く、酪農や馬は60~80%くらいでしょうか。ちなみに植物性堆肥はリン酸の肥効率は~50%です。ただでさえリン酸の含有量は少ないのに、~50%とは…。
窒素は、鶏は30~70%、豚は50%、牛糞や植物性堆肥は0~30%ほどが肥料として期待できると言われています。C/N比が20をこえてくると、肥効率は0%とも言われます。
あくまで目安ですし実際の堆肥や気候条件、土壌条件によっても異なります。また化成肥料と異なり、若干肥料効果が出るまでに時間がかかる場合も多いです。
肥料含有量の多い、鶏や豚はやはり肥効率も高く、牛も酪農よりも肉牛の方が肥効率は高い傾向にあります。つまり、原料やエサが植物性に近づくほど肥料として期待できる率も下がって来ると思っておけばおおむね間違いはなさそうです。

では、肥料成分も肥効率も少ない植物性堆肥の良さは何なのか…?
それはやはり、土壌改良効果の高さです。
特に物理性、生物性の改善で、これらが植物性堆肥の真骨頂です。
これはまた次回以降、お書きしたいと思います。